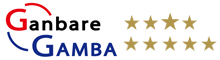【Jリーグ】柏レイソル指揮官リカルド・ロドリゲスは名将か 監督選びの根拠が薄弱すぎる
たとえば、日本代表を率いる森保一監督は「名将」と言えるか?
サンフレッチェ広島でJリーグを連覇しただけでも「名将」だろう。決して簡単なことではない。はっきりとしたプレーモデルも提示した。また、日本代表を率いて8年目になるが、その第1期はW杯アジア最終予選を勝ち抜き、カタール本大会でベスト16に駒を進めている。ドイツ、スペインに対する大番狂わせは語り草。今回の予選突破もほぼ間違いない。
そういう意味では岡田武史監督や西野朗監督も「名将」だろう。どちらもJリーグでタイトルを獲得し、日本代表をW杯ベスト16に導いた。その功績は傑出しており、彼らは飛びきりのボスだった。
ただ、この3人は世界的にも「名将」と言えるのか。その答えは、Jリーグで日本人監督がなかなか台頭しない現実とも交錯するかもしれない―――。
今シーズンのJリーグ序盤、評判を高めているのは、柏レイソルのスペイン人監督リカルド・ロドリゲスである。選手たちが、いつ、どこにいて、何をすべきか、その原則が通底されている。判断に迷いが少なくなった。それだけで主導権を握り、崩れかけても立て直すことができている。それを落とし込んだ監督の手腕が称賛されているのだ。
ただ、裏を返せば、昨シーズンまで率いた井原正巳監督が「凡庸だった」と言わざるを得ない。選手たちは最後まで、やるべきことに迷っていた。それは指揮官が「ハードワーク」や「気持ち」という抽象的な言葉でしか説明ができなかったからだろう。選手の動きに一貫性がなく、どのエリアが危険で、どのエリアがチャンスになるか、徹底がされなかった。
実際、J1の日本人監督で、瞠目に値するサッカーを展開する人材はなかなか見当たらない。ほとんど50代以上で、見知った顔ばかりだ。王者・ヴィッセル神戸の吉田孝行監督は若手だが、Jリーグでしばしば起こる「有力選手主導で強い」という現象だろう。神戸はミゲル・アンヘル・ロティーナ監督の解任前後から、主力選手主導でアンドレス・イニエスタ中心のサッカーと決別したことが結果につながった。
【監督経験が少ないまま迎えられる外国人監督】
では、リカルドは崇め奉るほどの指揮官か?
リカルドはスペイン国内での監督実績は乏しい。率いていたのは4部のチームが多く、2部ジローナではシーズン半分ももたずに解任されている。マラガ時代には、スポーツダイレクターとして1部に昇格、残留させた実績もあるように、目利きではあるが。
彼が監督としてのキャリアを形成したのは、皮肉にも徳島ヴォルティス、浦和レッズ、そして柏と、Jリーグなのである。
実はこうしたケースは他にもある。スペイン人監督のアルベル・プッチ(元アルビレックス新潟、FC東京)、ダニエル・ポヤトス(現ガンバ大阪、元徳島ヴォルテス)はリカルド以上にスペインでの監督経験がないが、長期プランで迎えられた。
クラブはなぜ日本人監督に投資せず、無名の外国人監督にチームを任せるのか。納得できる実績がないにもかかわらず……。
たとえば昨今の横浜F・マリノスはハリー・キューウェル、ジョン・ハッチソン、スティーブ・ホランドと、せいぜいリザーブチームの監督しかやったことがない人物に指揮権を与えている。キューウェルは選手時代の名声が豊富で、他もコーチとして在籍したクラブは立派だったが、監督としては素人同然だった。 「続けてもらえば成果が出る」とも言われたが、まるで呪文で、日本人に根強くある外国人コンプレックスかのようだった。
浦和レッズがマチェイ・スコルジャを呼び戻し、セレッソ大阪がアーサー・パパスを新たに招聘した理由をどう説明するのか。彼らは見識に優れた人物だろうが、監督選びの根拠は曖昧だ。
これは選ぶ側の問題だろう。どういうサッカーがしたくて、どんな監督を呼び、それに合った選手を集めるか。その一貫性のあるチームがJリーグには少ない。必然的に監督も「ハズレ」が増える。
昨シーズン、FC町田ゼルビアが躍進し、黒田剛監督は話題の人になった。多くの批判を受けたが、彼は”監督のなかの監督”と言える。高校年代とは言え、数十年に渡って監督として責任を背負い、勝負の最前線に立ってきたのだ。
【監督になるのが遅すぎる】
結局のところ、監督は覚悟を持って戦った場数次第なところがある。
少なくとも、監督ライセンスで名将は生まれない。アンバサダーや解説者やコーチに従事しながら、10年もかけてライセンスを取得するシステムは合理性に欠ける。時間がかかり過ぎるし、世界に比肩する監督が生まれるはずもない。
スペインでは30代後半から名将の威光のある監督が出ている。ジョゼップ・グアルディオラ(マンチェスター・シティ)、ウナイ・エメリ(アストン・ビラ)などはすでに熟練の域だが、シャビ・アロンソ(レバークーゼン)、アンドニ・イラオラ(ボーンマス)、ミケル・アルテタ(アーセナル)、イニゴ・ペレス(ラージョ・バジェカーノ)などが新たに台頭している。彼らは1年で最高位の監督ライセンスを取得し、引退後ただちに転身できているのだ。
「イングランドでは日本以上にライセンス取得が大変だ」と、日本のライセンス制度を正当化する声もあるが、イングランド人の名将はいるか。監督は教えられてなるポストではない。コーチとはまるで違うのだ。
今や日本人選手が当たり前のように欧州挑戦を続けているにもかかわらず、監督は国内で汲々としている状況にある。50歳前後で監督デビューする状況ではドメスティックにならざるを得ない。
選ぶ側が、真剣に良将を求めるべきだろう。
昨シーズンまでサガン鳥栖を率いた川井健太監督は成績不振を理由に解任されたが、筆者には、彼を在野のままにするなどクラブ側の見る目がなさすぎるように思える。傾いたチーム(現在の鳥栖の体たらくを見たらわかるだろう)で、彼がどれだけ選手の才能を目覚めさせ、上位クラブに送り出したか。選手を成長させることこそ、名将たる条件である。
日本に監督がいないわけではない。